恵比寿日和
2021年
大雪の初候は、「閉塞成冬(そらさむくふゆとなる)」。本格的な冬の訪れは雨催いではじまりました。
合羽坂テラスは、紅葉の盛りから冬寂びた風情へと移ろう狭間で、イロハモミジが一際艶やかです。
昔の人は、一面にモミシが散り敷いた様子を「紅葉筵(もみじむしろ)」と呼んだそうです。
川面に浮かべば「紅葉川」。散ってなお美しい紅葉に驚き、愛でる気持ちが伝わってきます。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん
小春日和が続きます。
大雪間近。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん
そろそろ雪が降りはじめる候。
ご近所の和菓子屋さんで亥の子餅が売られていました。
旧暦の十月は亥の月で、稲刈りが終わり、実りへの感謝と無病息災を祈って食べるもので、私の故郷では子供たちが藁に結んだ石で地面を搗いてまわる行事がありました。
明日は新嘗祭。
五穀豊穣への祈りと感謝は古今東西、今昔貴賤を問わず普遍的なものであるようです。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん
風に散る風葉が地面を彩る季節。
錦木(ニシキギ)はその名の通り、実に紅葉が見事です。
紅葉の多くは朱を含んだ赤が多いように思いますが、ニシキギのそれは紅色です。
合羽坂のテラスに舞い落ちる様は、薔薇の花びらを散らしたよう。
立冬の声を待っていたかのように気ぜわしく散りはじめました。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん
朝夕冷え込む季節。
テラスのイロハモミジも少しずつ色づいてきました。
今日は植物の紅葉の秘密について。
葉には様々な光合成色素が含まれていて、主なものは緑色をしたクロロフィルと黄味がかったカロテノイド。葉の老化が進むとクロロフィルが優先的に分解されるので、カロテノイドの黄色が目立ってくるそうです。
そして黄色から赤へと色を変えるのは、紅い色素であるアントシアニンが新たに生合成されるため。なぜ落葉の時期にわざわざエネルギーを使って新しい色素をつくりだすのか、長く定説が無かったようです。
ただ、有力な説となっているのが、アントシアニン日除け説。
タンパク質と結合せずに存在するアントシアニンは、分解する必要が無く、抗酸化作用という、いわば葉にとっての日除けの性質を効率的に果たせるため、と考えられています。
光合成色素は、光のエネルギーを吸収し、活性酸素の発生を抑える役割を果たしています。
落葉プロセスの中で色素は次々と分解・回収されますが、葉になんらかの色素を残しておかねばならず、アントシアニンはその役目を負っていると言われているのだそうです。
晴天が続くと、紅葉が一層鮮やかであるのは、太陽光線から葉を保護するためにアントシアニンが盛んにつくられるから。
色づくモミジの葉の中で、こんな精妙な化学変化が起きているのですね。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん
ホトトギスです。
秋の七草といってもキキョウやナデシコなど、今は夏の間に咲く感覚があります。
この時期に咲くホトトギスには秋咲く野花のイメージがあります。
東京は冷たい雨。
明日から二十四節気は霜降に移ります。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん
秋が深まり、露が冷たく感じられる頃。
移動性高気圧の影響で天候が安定し、秋晴れが似合う爽やかな季節といわれますが、今年はまだ汗ばむぬるさが残り、温暖化の余波を感じます。
この時期、合羽坂テラスではガマズミの赤い実が艶やかです。
果実酒やジャムになるのはよく知られています。
和ハーブ図鑑(和ハーブ協会出版)を見ると、青森のマタギの間では、深い山中で獲物を追っていて食べ物が尽きたときに、ガマズミの実で命を繋いだことから「神の実」が名前の由来になって「ジョミ」と呼ばれるとか。
土地土地で呼び名や伝説があるのは面白いです。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん
「里山ユニットに初めて実がつきました!」と写真付きでメールをいただきました。
5年ほど前にスリムタイプを購入いただいた方からで、
「ほんの小さな緑の実からの変化が見られて楽しいです」と、
写真にはまだ小さくて可愛らしい青いどんぐりと、茶色に色づいたどんぐりが!
高層マンションのバルコニーですくすくと育っている様子を垣間見ることができ、
とても嬉しくなりました。
「どんぐりが落ちたら、ぜひ土に植えてみてください」とお伝えしたところ、
「土を用意して準備万端で落下するのを待とうと思います」とのお返事も。
どんぐりがこの後どうなるか、楽しみに待ちたいと思います。



先日の選択除草(レポートはここから)では、全員ヌスビトハギからおみやげをもらいました。
写真のようにお洒落な色と形で、シャツやズボンにつくと、ワッペンでデザインされたよう。
かなり強くペタッと貼り付きます。
靴からバックまで全身コーディネートの人もいて、お互いに取りっこしたり、大わらわ。
種を運ぶ植物の戦略は色々ありますが、ヌスビトハギの接着力はなかやか優秀なようです。
合羽坂テラスのコナラに団栗(どんぐり)がなりました。
団栗というのは不思議なもので、その形状を人は可愛らしいと感じるからか、童謡になったり、店の名前になったり、格別愛重されているところがあります。
団栗はブナ科の果実の総称です。
植物がはじめて種をつくったのは3億6000万年前だそうで、それまでの胞子による生殖に比べて効率が良く、殻があることで乾燥に強く、休眠を可能にしました。
また、動物に果肉を食べてもらって種子を遠くまで運んでもらえるようになりました。
栄養価の高い団栗は、動物たちにとって魅力的な食べ物です。
団栗を拾って育てるワークショップなどがあると人もせっせと団栗を育てます。
その形状の愛らしさは生存戦略上有利に働くようです(笑)。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん
季節を分ける節目は色々ありますが、秋分はその代表選手といえるかもしれません。
秋立つ立秋から処暑、白露と季節は進んで秋もいよいよ本番です。
実りの秋、私たちが応援している馬頭の森からも新米が届きました。
森を訪れることも叶わず二度目の秋が過ぎようとしています。ゆるゆるとつづく里山を縁取る黄金色の風景へと、心だけ飛んでゆきます。
合羽坂テラスの楓たちもほんのり色づきはじめました。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん
今日、東京の空に鰯雲が綺麗でした。
久しぶりの青空に、秋の空の高さを思い出しました。
テラスの樹々の葉にも秋の色がにじんで、サマーグリーンからシックなオータムカラーへ変身中です。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん
暑さもそろそろやわらぐ候。
夏から秋へとふたつの季節が行き交う空を「行き合いの空」というそうです。
お盆が過ぎて、行き合いの空にも秋の気配を感じるようになりました。
テラスでは、深くなった緑にノシランの花の白さが際立っています。
ノシランの「ノシ」は、「熨斗」からきているとか。穢れを祓うような彩度の高い白です。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん
立秋を境に太陽と台風がせめぎ合っているような一日です。
「秋立ちぬ」と言われても、「どこに?」と聞きたくなる溽暑ながら、目を凝らすと季節は着実に歩みを進めています。
テラスのゴンズイの実が色づいてー。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん
炎帝がますます勢いを増したような日が続きます。
緑はいっそう深くなり、虫たちはせっせと仕事に励んでいます。
立秋の声が聞こえくる候。
「暑中見舞い」はまだまだ必要な陽気なのですけれど。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん
「暑いですね」が挨拶がわりになるここのところの猛暑です。
照りつける日射に比して深くなる緑陰に、小さなカマキリ。
虫たちは逞しく都心のテラスで生き抜いています。
二十四節気七十二候に「蟷螂生(かまきりしょうず)」というのがあります。(第二十五候)
してみると、このカマキリも六月の芒種の候に生まれたものでしょうか。
小さいながらも鎌は立派なものです。
おう なつだぜ
おれは げんきだぜ
あまり ちかよるな
おれの こころも かまも
どきどきするほど
ひかってるぜ
「おれはかまきり」という、よく知られたこの詩の作者、工藤直子さんは、小さなカマキリが一人前に鎌を振り上げている様子を見て詩を書いた、と語っているそうです。
カメラ目線ですが、「かまを ふりかざす すがた わくわくするほど きまってるぜ」と思っているのかも。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん
土用芽。
植物は春に新芽を出しますが、土用の頃にもうひと伸びします。
それにしても、コナラの新芽のこのコントラストはどうでしょう。
夏へ向けて濃さを増す緑に映える、銀色を纏った浅い緑。
古来から、植物が、人々の創造力にインスピレーションを与えてきたことも頷けます。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん
七夕の夜。
年に一度の逢瀬を今宵は果たせるかしら、と思ったところで、はて、織女と牽牛の恋ってどんなお伽話だったかしら?
幼い頃、あんなに一生懸命に短冊に願いを書いたのに、年古るごとに絵本で親しんだ物語の細部がぼやけてしまったようです。
雨に降り込められて仕事ができない時を「時の余」というとか。
梅雨がくれた時間をありがたく受け取って、忘れかけたお伽話を紐解くのも悪くないかもしれません。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん
ひと雨ごとに緑が深くなる季節になりました。
合羽坂テラスには、里山のように色々な種類の植物が共生していますが、緑が織りなすデザインに心打たれます。
写真の中で鳥の羽が並んだような葉っぱのリズムを刻んでいるのは合歓木。夏の季語でもあります。
雨に濡れた緑が、梅雨明かりの中に浮かんだ様子には格別のものがあります。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん
一年で昼の時間が最も長く、夜が短い。
季語で夏は短夜。
暦では、立夏から夏ですが、天文学では今日から夏です。
そして、何より植物たちが勢いを増す季節。
合羽坂テラスの里山ユニットの土の厚さは25cm。その中で精一杯伸ばした枝葉がテラスに青い天井をつくっています。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん
芒種の末候は、梅子黄(うめのみきばむ)。
合羽坂テラスの前庭にある小さな梅の木。
木は小さくても実は立派です。
落果は、熟す前に落ちてしまった果実。
熟して落ちるのは臍落(ほぞおち)といいます。
夏至間近、臍落ちの梅の実が、木の根元に忘れられて。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん
関東地方も入梅しました。
梅雨と聞いて思い浮かぶ植物はやはり紫陽花でしょうか。
合羽坂テラスの前庭にも紫陽花が日々花の色を濃くしています。
この紫陽花もそうですが、町で見かける紫陽花の多くは、母種は額紫陽花で、品種改良が進んで装飾花が球の形になりました。
これを「手毬咲」ともいうそうです。
在来種の5×緑で扱うのは、額紫陽花や草紫陽花が中心です。
よく知られるように、シーボルトがこの花を西欧に紹介するとき、愛する女性「お滝さん」の名を忍ばせてotakusaと呼んだとの説があります。真偽のほどは長雨の向こうに霞んではっきりしないようです。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん
芒種の次候は、腐草為蛍(くされたるくさほたるとなる)
昔の人は、腐った草が蛍になると信じていたそうです。
なんと不思議で美しい想念でしょう。
合羽坂のテラスには少し前から下野が咲いています。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん
稲や麦の種を蒔く季節。
イネ化の植物の穂先の針を芒(のぎ)というのだそうです。
今日は「環境の日」。「世界環境デー」でもあります。
ストックホルムで開かれた「国連人間環境会議」を記念しているそうですが、緑の勢いが増してくるこの時期に、山や森やそこに生きる生き物たちに思いを馳せるには良い季節なのかもしれません。
合羽坂テラスの樹々も勢いよく伸びて、テラスから溢れています。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん
植物の精気が満る候、テラスの小さな枇杷の実も精一杯満ちてー。
この枇杷、実はスタッフのお子さんが食べた種から発芽して育ったのです。
枇杷は薬効に優れ、「大薬王樹」の異名があるほど。なんだか今時のアニメに出てきそうな名前ですね。
江戸時代には暑気払いに「枇杷薬湯」をふるまう習慣があったそうです。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん
陽気盛んにして、万物が次第に長じ、天地に満つる候。
大きな実りへ向けて生命が次第に満ちてゆく時候、ということでしょうか。
テラスのネズミモチももうすぐ開花しそうです。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん
モミジは秋と思いがち。
でもー。
モミジ、カエデの萌え出る瑞々しさは格別で、この時期は「若楓」と呼び慣わされています。
兼好法師もその美しさを愛し、「徒然草」に「卯月ばかりの若楓、すべて、万の花、紅葉にもまさりてめでたきものなり」と記しています。
ベタ褒めですね。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん
風薫る五月。
緑を渡る風には、樹木の精気に混じって、テイカカズラやらエゴやらユズやら、花々の香りが混じって五感を呼び覚ますような爽やかさがあります。
薫風、若葉風、緑風と、この時期の風の表現も様々。
立夏は風のなかにあり。
テラスのエゴも花を咲かせました。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん
♪夏も近づく八十八夜
野にも山にも若葉が茂り
今日は八十八夜。
東京真ん中、テラスの若葉もご覧のとおり。
♪軒も屋根にも若葉が茂りーと言ったところでしょうか。
立夏も間近。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん
田畑を潤す恵みの雨の季節。
春雨も色々。
小糠雨、春に限った雨ではないですが、細かく柔らかい雨は、しっとりと大地を潤す感じがこの季節ならではの趣きです。
雨が続くと菜種梅雨、夕立のようなにわか雨なら春驟雨。
五風十雨という言葉もあります。
五日ごとに風が吹き、十日ごとに雨が降る、農作に適した天候で、穏やかで順調な様子を表しています。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん
躑躅考。
ツツジの漢字は躑躅(てきちょく)と同じです。
躑躅(てきちょく)とは、「足踏みすること。ためらうこと。ちゅうちょ」(広辞苑)
どうして、このような意味を持つ、難しい字が当てられたのか不思議です。
古くから日本に自生していますが、品種交配によって種類も多く、江戸時代には「元禄の躑躅ブーム」が起きたとか。
和歌や俳句、文学にも、躑躅はたくさん登場します。
泉鏡花の小説に「五月五日躑躅の花盛んなりし」という一節があるそうで、やはり花の盛りは黄金週間の頃。
晴明の候に咲くとは、昔ながらの季節の感覚とずれてしまいそうです。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん
5年前、創立80周年を記念して、本社足元の植栽を手がけさせていただいたスターライト工業さんから、筍が届きました。
スターライト工業さんは、滋賀の栗東に工場があり、ここで採れた筍をたくさん送ってくださったのです。
栗東工場には、豊かに植物が茂り、とくにシダレエンジュのコレクションは見事です。
そんなお施主様だけに、緊張しながら、でもやりがいの大きい仕事だったことを懐かしく思い出しました。
丁寧な御手紙と共に、米糠と筍の調理方法を詳しく書いた説明書も同封されていて、彼の社の人柄が偲ばれます。
(会社にも人柄ってありますよね)
旬の味わいの嬉しさと合わせて、こうして縁を繋げて頂いていることがありがたく。
合羽坂テラスには八重に咲く桜の古木があります。
毎年、今くらいに満開を迎えるのですが、今年は開花が早く、ベランダにハラハラと花弁を散らしています。
かつては、桜同士を掛け合わせてさかんに園芸種がつくられました。それを総称して里桜といいますが、合羽坂テラスの桜も里桜。「一葉」という種類だと思います。
八重桜は、ぽってりとした紅色のものが多いですが、「一葉」は、蕾の間は愛らしい紅で、花が開くほど白く、愛らしさと気品を合わせ持つ桜だと思います。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん
「晴明」は「晴浄明潔」の略だそうです。
万物が清らかで明るい、麗かな春の精気を感じます。
里山ユニットに、躑躅の花が咲きました。
街でも身近な躑躅の花。歩道ややビルの足元に列植されて華やかに咲いているのを見かけます。
でも、躑躅の美しさに気づいたのは森のなかでした。
新緑の中に点在する鮮やかな朱。
萌える緑の下枝の間から覗くその鮮やかさにハッとしました。
この花を見ると、目の前に青やぐ森の風景が広がります。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん
今年は桜も咲き急いだようです。
大勢が愛でる桜の花をよそ目にひっそり咲く花も。
ヒサカキの花をご存じですか。
冬でも艶やかな緑の葉を保つサカキやヒサカキは、常若のイメージと重なるのか、神事にも使われる神聖な存在です。
ですが、花は小さく目立たず、枝の下に付くのでなおさら人目を引きません。
でも、虫たちはようく知っています。
ほら、蜂がテラスの里山ユニットにも。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん
薹(とう)が立つ―--。
この時期の蕗の薹を見ると、ついこの言葉が浮かんできます。
野菜の芯が育ち過ぎて食べ頃を過ぎてしまった様子をいいます。
茎立とも。
「嫁にいくには薹がたちすぎている」
こんな台詞は今はもう死語ですが。
5×緑の里山ユニットの蕗も、おかまいなしににょきにょき!立派に薹を立たせています。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん
「あぁ、春だ」
心の中にこの言葉を思い浮かべるだけで、ふわりと歓びが湧き上がってくるから不思議です。
植物たちの緑の上で光の粒が躍っています。
合羽坂テラスにも春がやってきました。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん
東京でも14日に、桜の開花宣言が発表されました。
ハラハラと花弁を散らす桜の花は、「もののあはれ」を尊ぶ日本人の心を捉えてきました。
今風に言えば「エモい」というのでしょうか。
桜の散り様と対照的なのが椿の花。
落花の時は花全体がポトリと落ちます。
合羽坂テラスの庭にも小さな椿が一本。
「落椿」は、春の季語。万葉の時代から歌に詠まれてきました。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん
合羽坂テラスは1970年代に建てられた3階建ての集合住宅です。今では贅沢な前庭があって、桜の古木や小さな梅の木や皐月や紫陽花が植えられています。
木々があるおかげで、こんな都会の真ん中の庭にも、メジロやらヒヨドリやらがやってきます。
啓蟄を啣(くわ)へて雀飛びにけり 川端茅舎

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん
木の芽雨が降りたそうにしている東京の空です。
季節は啓蟄。
二十四節気のなかでは、わりあい知られている節気ではないかと思います。
啓蟄は、冬を地中で過ごした虫や蛇や蛙らが、土の上に顔を出す様子を意味しています。
人工土壌を使った新宿のテラスの5×緑のユニットの土の中でも、何やら蠢きが。ふわふわと「春のけわい」がここにも。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん
雪が溶けて水になり、降る雪が雨に変わるころ。
草木が芽吹始める春の野を「萌野」、そして地面から草の芽が萌えるでることを「下萌え」というそうです。
都会のテラスにも、目を凝らすと萌える春が訪れています。
芽生えたばかりの柔らかな若葉と、恵みの雨の水滴が仲良く並んで。
上を向いているのが若葉、下に向いている水滴、春のリズムを奏でているよう。

写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん
立春の空。
立春は、二十四節気のはじまり。旧暦では一年のはじまりでもあります。
生まれたての春がきらきらと輝くような清々しさを感じます。
そういえば「風光る」は、春の季語。
春待ち顔の枝が、風光る空へ伸びていました。
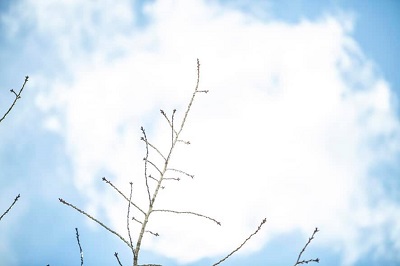
写真:新宿 合羽坂テラスから 撮影 masacoさん

ベランダの里山ユニットのシャガが満開です。
ベランダで、春を眺める。小さいながらシャガの花が誇らしげに咲いていて、若葉も日に日に膨らんでいる。
ささやかですが、心和むひとときーーなのは間違いないのですが、春分を過ぎたとはいえ、まだ3月。
シャガが咲くには早すぎるのでは?と驚きました。
今年の桜は咲き急いだようですが、年々季節の進み方が早くなるようで、気候変動と重なって心配になります。
先日も、知り合いの方からヤマブキが花を開いていているらしい、とお知らせがありました。
5月の連休頃に咲くものだと思っていました、と。
あぁ、確かに。ヤマブキも今日は満開でした。
都内で拾ったコナラのどんぐりから、可愛らしい芽が出ました。
コナラの新芽は銀色の産毛に包まれていて、好きな若葉の一つです。
大木になると、春の日差しを浴びて銀色に輝くようで、荘厳ともいえる姿です。
その大木も、こうしてどんぐりから芽を出して育っていったのですね。


初候
第七十侯「ふきのとう、咲く」
今日は大寒らしい厳しい寒さですね。
「ふきのとう」はまだ先のようですが、
コブシの蕾は先月よりも少し大きくなったように思います。
春が待ち遠しい。

次候
第七十一侯「水沢、氷を張る」
ナンテンの実生(みしょう)を見つけました。
枯葉の中に紅一点、愛らしく主張していました。
合羽坂テラスより

末候
第七十二侯「鶏、はじめて卵を抱き始める」
七十二候も一巡りして、最後の候となりました。
七十二候は、二十四節気を更に「初候」「次候」「末候」の
三つに分けてつくられています。
第七十二候は、「大寒」の「末候」。冬の終わりとも言えます。
毎年手にさせていただく「和暦日々是好日」の中で、
制作者の高月美樹さんは、こんな風に記しています。
***
自然と一体になって暮らしていた昔の人々は「気配」や「兆し」に敏感でした。
それぞれの季節には「生、旺、墓」があり、ひとつの季節が頂点を迎えた瞬間に、
次の季節の生まれたことを感じていたのです。
***
そんな四季の変化を感じにくくなった都会暮らしの中でも、
目を凝らせば季節は着実に巡っているーー
そんなことを植物たちを通してお伝えしたくて、
SNSで「ベランダ森化」を始めました。
私たちのオフィスがある新宿の合羽坂テラスには、
5×緑の里山ユニットが並んでいます。
私たちは、そこで、都心の限られたスペースであっても、
営まれるいのちの巡りのあることを知りました。
花が咲き、実を結び、葉を落とし、また若葉が萌える、
そんな変化を身近に見てきました。
打ち合わせのガラス越しに、鳥が水浴びをしている様子を見たことも、
アオスジアゲハの幼虫の育ちを見届けたことも、
カマキリの赤ちゃんを見つけたこともありました。
並んでいる里山ユニットの枯葉を掻き分けると、
そこに芽生えたばかりの小さなユキノシタをみつけることができました。
冬の終わりに春の兆しをみつける、そんな喜びを大切にしたいと思います。
もうすぐ立春。
春からは、二十四節気ごとに、この合羽坂テラスから季節の便りをお届けします。
写真は、写真家のmasacoさんにお願いすることになりました。
どうぞお楽しみに。

初候
第六十七候「芹、盛んに育つ」
新年あけましておめでとうございます。
三が日は天気も良くて
気持ちの良い新年の幕開けとなりました。
元日、散歩をしていたら、
「この時期に白い花が満開?」という樹に会いました。
答えは花ではなくて、
ナンキンハゼの白い種子。
秋には紅葉も美しくて、
四季を通じて楽しませてくれる
中国産の落葉樹でした。


次候
第六十ハ候「地中の清水、動き始める」
夕方ふと空を見上げたら、落葉した寒々しい樹木から、月が覗いていました。
大寒よりも小寒のほうが寒気を感じることがあるそうです。

末候
第六十九侯「雉、鳴く」
雉は、万葉集にも登場する日本の国鳥。求愛の鳴き声は、
春の兆しを感じさせるものだったのかもしれません。
「雉、鳴く」は小寒の末候。大寒も目の前です。一年で一番寒い季節。
でも、季節は春を胚胎しながら進んでいきます。
樹々の冬芽の膨らみが私たちにそのことを教えてくれます。
(写真はシラカシの冬芽です)

初候
第六十四侯「夏枯草、芽を出す」
寒いですね。
空気が澄んで、
ソヨゴの赤い実も艷やか。
今日は冬至、ゆず湯でゆっくり温もりたいですね。

次候
第六十五侯「大鹿、角を落とす」
合羽坂テラス、今年最後のテイカカズラの実。
実がパンと割れ種がいまか、いまかと巣立つのを待ってる様。
種には鳥の産毛のようなふわふわ艶艶の羽を持っていて、
巣立つという言葉がぴったりな気がします。
風に乗ってどこに行くのでしょうか。

末候
第六十六侯「雪の下で、麦の芽のびる」
七十二候の中でも好きな一候です。
季節の言葉は、この頃から次第に春の兆しが感じられるようになってきます。
さて、年の瀬になると気になるのが我が家の小庭の千両の実です。
大晦日まで待って、ひと枝正月飾りにもらうのですが、一昨年も昨年も、
それより前に鳥たちに食べ尽くされてしまいました。
元々、この千両は、鳥たちが運んでくれたもの。
優先権は彼らにあるので仕方がありません。
この冬も南天が早くからなくなってしまったので、諦めていましたが、
今年はちゃんと残してくれたようです。
それはそれで、どうしたのだろうと気にはなるのですが。
一年の終わりを表す言葉は色々ありますが、年の湊もその一つ。
希望をたくさん積み込んで、新しい年へ佳き舟出を。

初候
第六十一侯「天地寒く、真冬となる」
葉裏からの葉脈がとてもきれいで、
思わず撮った一枚。
今日はニ十四節気 大雪。
テラスの紅葉もいよいよ終盤です。

次候
第六十二候「熊、穴にこもる」
花が咲いているのかと思ったら、アケビの葉っぱでした。
合羽坂テラスにて


末候
第六十三侯「鮭、群がって川を上る」
新年の声が聞こえてくる季節。
お正月に飾られる万両、千両、十両、艶々の赤い実の揃い踏み。
合わせて一万一千十両!?

初候
第五十八侯「陽射しが弱まり、虹を見なくなる」
隣の雑木林も
すっかり秋色になりました。

次候
第五十九侯「北風、木の葉を払う」
うちの柿の葉も北風で全て払われていました。
いよいよ冬ですね。
仲間のお子さんがビワの種から育てた木が、
縁あって合羽坂テラスの森に植えてあります。
10?12年目に初めて花が咲きました。
来年は実をつけますように!

末候
第六十侯「橘、初めて黄ばむ」
昔の人はこんなところにも季節の変化を感じ取っていたのですね。
橘ではないけれど、合羽坂テラスの金柑はこんなです。

初候
第五十二候「初霜が降りる」
合羽坂の小さな秋。
カキノキ、ガマズミ、コマユミ。



次候
第五十三候「「雨、時々ふる」
庭のツワブキにたくさん蕾ががつきました。
フキに似た艶のある葉からツワブキになったと言われています。
合羽坂テラスの食べられるユニットには、ツワブキとフキが植わっています。


末候
第五十四侯 楓蔦、黄ばむ
電車の中で、軌道敷きに生茂るセイタカアワダチソウを見て、
ご婦人がお隣の男性に「ほら、見て。女郎花があんなに。
見事ねぇ。秋の七草よ」とお話しされていました。
確かに今では、東京の秋の七草はセイタカアワダチソウなのかもしれません。
楓も蔦も秋色の候、万両の実も色づきはじめました。

初候
第四十九侯「北から雁がやってくる」
暦のうえでは、秋晴れが続く季節ですが、今年は週末の台風が心配ですね。
先日の選択除草で、たわわに実る銀杏を見つけました。
秋が深まり始める頃です。


次候
第五十侯「菊の花、咲く」
秋の風景に溶け込んで目立ちすぎず、
でも色を添えているオミナエシがあまりにも可愛くて、、
10/3選択除草より

末候
第五十一侯 蟋蟀、戸口で鳴く
植物のこんなところにやられてしまうのです。
小さなアプローチガーデンができた時にやってきた月桂樹。
最初から黒スス病にかかってしまってずっと調子が悪く、
木酢液を撒いたりもしたのだけれど、なかなか良くならないままでした。
それでも枯れもせず、20年もずっと我が家の庭にいたのですが、今年の猛暑!
夏の終わりに茶色く枯れる葉が出てきて、こんなことは初めてで驚いて、
心配していたのですが、ある日見ると、茶色くなった葉っぱの間から若芽が!
植物のこんな姿ににいつも元気をもらいます。

初候
第四十六侯「雷、声を収む」

次候
第四十七候「虫がかくれて、戸をふさぐ」
ゴンズイの果実が熟して裂けました。
1個の花から3個の果実ができるそうです。

末候
第四十八侯 水田の水を抜く
キンエノコログサが秋の日差しに輝きながら風に揺れていました。
外来種を除いて在来種を残す選択除草を続けている「みどりの広場」。
チカラシバとキンエノコロ、そして虫たちの王国になっていました。
波打つようなチカラシバの合間にオミナエシが顔を出し、
カントウヨメナやミズヒキの群生が草原に色を添えています。
こんな草っ原も最近見なくなりました。
これまでの選択除草で確認された在来種は115種類に上ります。

初候
第四十三侯「草に宿った露が白くなる」
台風の影響でコナラやクヌギの大木も大きく揺れています。
よく見るとクヌギにどんぐりががたくさん実っています。
秋が近づいていますね。

次候
第四十四「鶺鴒(セキレイ)、鳴く」
7月ごろから次々と花を付けているヒヨドリジョウゴ。
実を付けてもまだまだ咲き続けています。


末候
第四十五侯 燕、南へ去る
今年の夏は暑かった!
9月に入っても連続の猛暑日。
いつもはわんわん伸びるテイカカズラも、今年は暑さに伸びるのを控え気味です。
そんな中でも葉を開こうと、枝先に小さな新芽をみつけました。
一生懸命さが健気です。

初候
第四十侯「綿のはなしべ、開く」
我が家のユニットに、
初めてコバギボウシの花が咲きました。

次候
第四十一侯「天地の暑さ、ようやく鎮まる」
合羽坂テラスでみつけた実、テイカカズラ、ゴンズイ、スギ、ガマズミ。
樹種によって形が様々で、実が熟し種子になって次の命に繋げる(子孫を残す)
究極の形なんですね。

末候
第四十二侯 稲の穂、実る
我が家の里山ユニットのテイカカズラにはじめて実がなりました。
土は、わずかに30cm角しかありません。
そこに植えたテイカカズラ、にしては立派で大きな実二つもついて、
なんだか「お前も一人前になったね、エライね」
と声をかけてかけてあげたくなるようなー(親バカっ!?)
テイカカズラの実は豆の鞘のように見えますが、やがて茶色くなって割け、
冠毛につつまれた小さな種が、風に乗って飛んでゆくようにできています。

初候
第三十七侯「かすかに涼風が立ち始める」
ようやく夏らしくなってきたところですが、今日は立秋。
歩いていたら、秋の七草、萩を見つけました。

次候
第三十八侯「蜩(ひぐらし)が鳴き始める」
ニシキギの若い実。
撮った角度のせいか、クリオネに似て可愛いらしい。
秋には葉も実も綺麗な赤色になります。

末候
第三十九侯 深い霧が舞い降りる
立秋も過ぎたというのに、連日記録的な猛暑に見舞われています。
伊勢神宮下宮参道の入口にあるホテルのフロントロビーを飾る里山ユニット。
夏の日差しを浴びてホトトギスが力強く咲いていました。
赤紫の斑紋が、鳥の時鳥の胸の模様に似ているのが名前の由来と言われています。
夏の光の中、赤紫の斑紋もひときわ鮮やかでした。

初候
第三十四侯「桐の花 、実を結ぶ」
テイカカズラのお手入れ第二段。
丁寧にツルをピンチすると、
写真のように葉っぱは密になります。
写真は6年前にお庭を作らせていただいたお宅の様子です。
奥様の手入れの賜物です!


次候
第三十五侯「土潤いて、蒸し暑し」
合羽坂テラスの緑もだんだん深くなってきました。
毎日雨ばかりですが、雨も素敵に思えるテラスの森です。

末候
第三十六侯 時折、大雨が降る
入道雲に夕立ち。盛夏の侯。
今年、関東は昨日ようやく梅雨明けしましたが、来週は、はや立秋。
なんて短い夏でしょう。
写真は京都の壁面緑化に咲いた、女郎花。
秋の七草の一つです

初候
第三十一侯「梅雨が明け、熱風吹き始める」
テイカカズラの花も終わってツルがぐんぐん伸びてきました。
葉と葉の間が空いたツルは、
元気な双葉の上から、
思い切ってツルを切ってみてください。
テイカカズラのお手入れ、お願いします。



次候
第三十二侯「蓮の花、初めてひらく」
水盤ユニットに咲くコバギボウシ。
後ろ姿ですが、、

末候
第三十三侯 鷹の雛、飛ぶ技を習う
雛の巣立ちの候、5×緑の新しい緑化ユニットの生産拠点「5×緑 BASE」が
少しずつ稼働し始めました。
今日はみんなで、西風対策の生け垣を植えました。
風、雨、日差し、、、自然と上手に折り合いをつけられるか心配です。
巣立つ雛のごとく、私たちも一つ一つ学びながら、
ここで、街に届ける緑を育みます。



初候
第ニ十ハ侯「夏枯草、枯れる」
今日は東京郊外にある幼稚園の
メンテナンスに来ています。
去年はここでウツボグサがたくさん
咲いていましたが、
今年はオカトラノオが元気です。
グラスダイヤモンドフェンスも
テイカカズラか充実してきました。



次候
第二十九侯「菖蒲の花が咲く」
梅雨のあいまの太陽。
草木が嬉しそうに輝いています。
すっかり緑が深くなりました。
合羽坂テラスより

末候
第三十侯 半夏、生じる
半夏(カラスビシャク)の生える候。
今日は一日大雨になったり小雨になったり。
この頃降る雨は「半夏雨」と呼ぶそうで、大雨になることが多いとか。
里山ユニットのキキョウも雨に打たれて。。。
一年も、折り返しです。


クリスマスの日。秋に里山ユニットをお届けし、テラスを"森化"してくださった方から、里山ユニットを絵葉書にしたお便りが届きました。
植物たちを慈しんでくださっている様子がつたわってくる文面。
私たちにとっては何よりのクリスマスカードになりました。
新築のご自宅は、鹿児島でカッコいい住宅をつくっているベガハウスさんの手になるもの。
素敵な空間に迎えられて、緑も一段と映えるようです。
最近の記事
- 2025.07.06 田島ヶ原観察記録
2025年11月17日 - 2025.06.08 田島ヶ原観察記録
2025年11月 6日 - 2025.05.17 田島ヶ原観察記録
2025年9月19日 - 2025.04.29 田島ヶ原観察記録
2025年5月14日 - 2025.04.05 田島ヶ原観察記録
2025年4月23日













